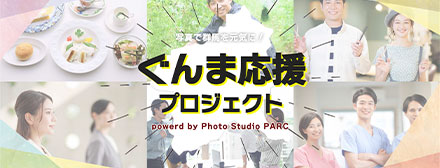七五三とは?伝統と由来を徹底解説!

七五三(しちごさん)は、日本の伝統的な行事で、3歳・5歳・7歳の子どもの成長を祝う儀式です。もともとは平安時代の宮中行事が由来とされ、江戸時代には武家を中心に広まり、やがて庶民にも定着しました。現在では、家族で神社に参拝し、子どもの健康と成長を願うイベントとして親しまれています。
① 七五三の由来と歴史 🏯
七五三の起源は、平安時代の宮廷で行われていた「髪置き(かみおき)」「袴着(はかまぎ)」「帯解き(おびとき)」という儀式にさかのぼります。
| 年齢 | 由来となった儀式 | 内容 |
|---|---|---|
| 3歳(男女) | 髪置きの儀 | 幼児期に剃っていた髪を伸ばし始める |
| 5歳(男の子) | 袴着の儀 | 初めて袴を着用する |
| 7歳(女の子) | 帯解きの儀 | 幼児用の紐付き着物から、大人と同じ帯の着物を着る |
このように、子どもが成長の節目を迎えるごとに新たな装いをし、大人への第一歩を踏み出す儀式として行われてきました。
江戸時代になると、武家社会でこの習慣が広まり、庶民の間でも「子どもの健やかな成長を願う行事」として定着しました。
② 七五三の意味 🎌
七五三は、子どもの成長と健康を願うとともに、神様に感謝する儀式です。日本では古来、7歳までは神の子とされていました。7歳になることで、正式に社会の一員として認められるという考えがあり、七五三はその区切りの意味を持っています。
また、「7」「5」「3」という数字は縁起が良いとされ、日本では奇数が吉数(縁起が良い数)とされています。そのため、3歳・5歳・7歳の年齢でお祝いをするようになりました。
③ 七五三はいつ祝う? 📅

七五三の日は「11月15日」とされています。
🔹 なぜ11月15日なの?
この日は、江戸時代に徳川綱吉の息子・徳松の健康を祈った日であり、これが七五三の行事として広まったと言われています。また、旧暦では鬼が出歩かない「鬼宿日(きしゅくにち)」にあたり、特にお祝いごとに適した日とされていました。
🔹 いつお参りすればいい?
近年では、11月15日にこだわらず、10月〜12月の週末や家族の都合の良い日にお参りする家庭が増えています。
④ 七五三の祝い方 ⛩️
🔹 神社へのお参り
七五三では、子どもが健康に成長したことを感謝し、今後の無事を祈るために神社へ参拝します。
ご祈祷を受ける場合は、事前に神社で予約が必要なこともあります。
🔹 千歳飴(ちとせあめ) 🍬
七五三といえば、「千歳飴」も欠かせません!
✅ 細長い飴 → 長寿を願う
✅ 赤や白の色 → 縁起が良い
✅ 袋に描かれた鶴や亀 → 長生きの象徴
千歳飴を食べることは、子どもの健やかな成長を願う意味があるので、ぜひ一緒に楽しみましょう。
🔹 衣装・記念撮影

神社参拝とは別日に写真スタジオで記念撮影をする家庭も増えています。
着物だけでなく、洋装でドレスやスーツを着るスタイルも人気です。
⑤ まとめ 🌟
✅ 七五三は「3歳・5歳・7歳」の成長を祝う行事!
✅ 起源は平安時代の「髪置き・袴着・帯解き」の儀式
✅ 11月15日が正式な七五三の日だが、最近は家族の都合に合わせてお祝いすることも◎
✅ 神社参拝、千歳飴、記念撮影など、それぞれの家庭に合った形で楽しもう!
日本の伝統行事である七五三を、家族みんなで楽しくお祝いしましょう! 🎉